日本語から離れたい!という決意
中国留学が始まったとき、私は同じ大学から来た日本人の同級生と同じ部屋に入ることになりました。
でも「中国に来たからにはできるだけ日本語から離れたい」と思っていた私は、自然と彼女との距離を取るようになっていきました。
避けていたわけではないけれど、なんとなく居心地が合わなかったのも事実。
次第に一緒に行動することも減り、私は少しずつ別の交流を求めていくことにしました。
韓国人ルームメイトとの出会い
その後、一緒に暮らすことになったのは韓国人の同居人。
金髪で小柄な彼女は、まるで自由そのもの。
授業に真面目に出る様子はなく、遊びの中で中国語をどんどん習得していくタイプでした。そんな彼女のかわいらしいところは、一緒の部屋になり始めたころ『ランチに一緒にサンドイッチを作ろう!』と誘ってくれたこと。こんな人懐こいところもあるから、友達もたくさんいて、交友関係の広さやフットワークの軽さは今でも尊敬に値するなと感じています。
部屋にはほとんどいなかったルームメイト。一方、私は規則正しい生活を心がけ、授業にもきちんと出席。
夜、部屋で休んでいるときも、彼女はほとんど不在。
「これ、ルームメイトの意味ある?」と心の中でつぶやいたこともあります。
極めつけは、寮で禁止されている犬を飼い始めたこと。
ある夜、寝ている私の顔をその犬がなめて起こされたときには、本当にびっくりしました(笑)。
(犬が嫌いなわけじゃないのですが、ふいを突かれるとさすがに驚きます…。)
共同生活の難しさ
生活習慣がまったく合わず、一緒に暮らすことが正直つらくなっていました。もしかしたら真面目に勉強しているのになかなか語学力が伸びない自分と遊んでいるのに中国語がペラペラな彼女を比較して、そんな状況がしんどかったのもあるのかもしれません。
ちょうどそのころ授業が夏休みに入り、寮を一旦出ることに。
今振り返ると「共同生活は私には不向きだった」と気づくきっかけにもなりました。
でも、それも含めて貴重な経験。
異国の地で、初めての“親元を離れた暮らし”が私を少しずつ鍛えていったのです。
忘れられないビーフシチュー事件
そして、今でも笑ってしまうのが「鍋ごと消えた事件」。
寮の共同キッチンでビーフシチューを煮込んでいたのですが、部屋に戻って数分後、鍋を取りに行ったら――あら不思議、鍋そのものが跡形もなく消えていたのです(笑)。
あのときの呆然とした気持ちは、今でも鮮明に覚えています。
国際色豊かな仲間たち
寮には、日本人、韓国人、北朝鮮人、タイ人など、さまざまな国からの留学生が暮らしていました。
最初は戸惑いの連続でしたが、しばらく経つとその国際色豊かな環境にも少しずつ慣れていきました。
結び
初めての中国留学生活は、文化や言葉の壁だけでなく、共同生活の難しさに直面する日々でもありました。
でも、そこには「鍋ごと消える」という信じられないような事件や、国際色豊かな人たちとの交流もあって、後から振り返ると宝物のような思い出です。
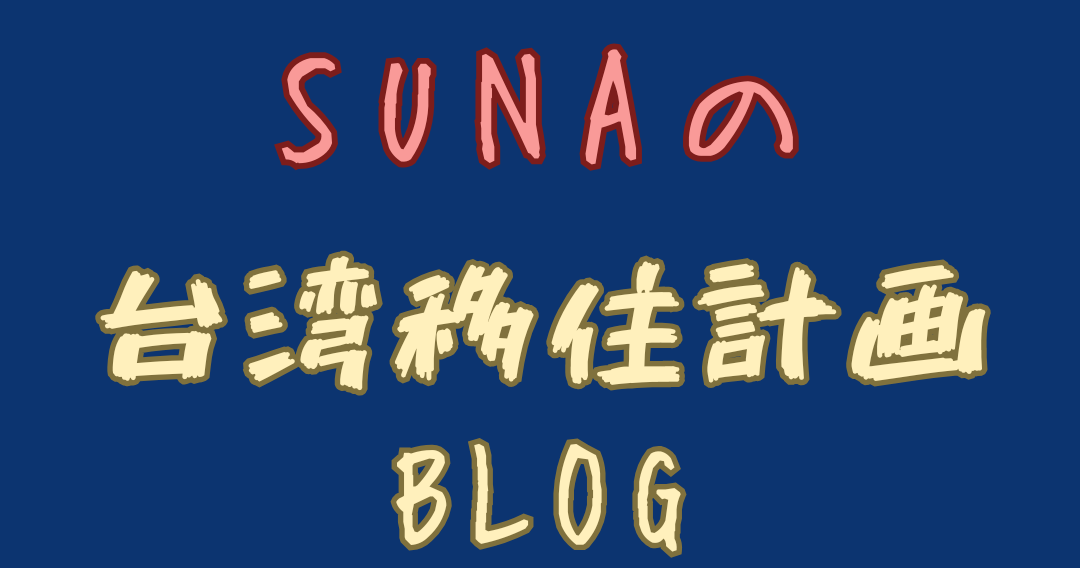

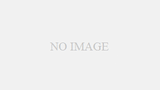
コメント